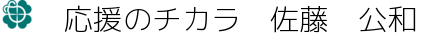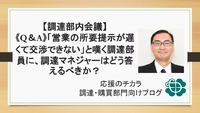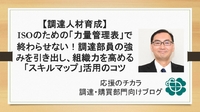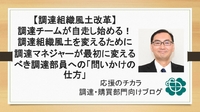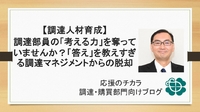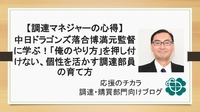- ホーム
- ブログ
- 「企業研修」関連記事
- 【研修担当者向け】調整・交渉力の高い人がやっている習慣3つ
【研修担当者向け】調整・交渉力の高い人がやっている習慣3つ

- 調整・交渉をテーマにした研修を検討していて・・・。
- 研修に調整・交渉力を高める習慣について触れてほしいが・・・。
- どのような習慣を取り入れたらいいか教えてほしい!
このような課題をお持ちの研修担当者の方へ。
調整・交渉力を高めるための習慣・・・。どんなものを取り入れたらいいかピンと来ないですよね。
調整・交渉力を高める習慣を取り入れることができれば、研修で学んだことを定着できるので大切ですとお伝えしています。
【研修担当者向け】調整・交渉力の高い人がやっている習慣3つ
習慣①「お願い」して対応してもらえる方法がないか考えている
1つ目の習慣は、「お願い」して対応してもらえる方法がないか考えていることです。
これは、調整・交渉せずお願いしてやってもらえるならその方がいいからです。そのためには、お願いしたいことが「無理やり」だったり、「できないこと」でないかを事前にチェックすることが必要です。相手に「お願いしても大丈夫そうだな」という内容に絞って打診することを習慣にしています。
習慣② 相手が困っていることを解決できるように協力する
2つ目の習慣は、相手が困っていることを解決できるように協力することです。
これは、調整・交渉場面で「この問題は相手に責任があるのだからこちらは関係ない」というふうに突き放してしまうと、調整・交渉のゴールに近づくことができないからです。
「相手の問題は自分の問題でもある」と捉えて、どうしたら解決できるか一緒に考える習慣を持っていれば、自然と調整・交渉力が高まります。
習慣③ 相手が気持ちよく対応してもらえるように動機づけを意識している
3つ目の習慣は、相手が気持ちよく対応してもらえるように動機づけを意識していることです。
調整・交渉場面で合意ができても、実行されなければゴールではありません。
ゴールに到達するにはお互いにすべきことを進めていく必要があります。調整・交渉相手に協力を求めることも出てきますが、そのときに気持ちよく対応してもらえるように動機づけ(行動を促す)まで意識する習慣を持っていると、スムーズに進めることができます。
まとめ
- 習慣①「お願い」して対応してもらえる方法がないか考えている
- 習慣② 相手が困っていることを解決できるように協力する
- 習慣③ 相手が気持ちよく対応してもらえるように動機づけを意識している
調整・交渉力が高い人は、調整・交渉していることを意識せずに対応できるようになっています。そのためには調整・交渉力を高める習慣を身につけることが重要です。応援のチカラでは、調整・交渉力を高める習慣についても研修プログラムに盛り込むことが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
研修担当者様、調達マネジャー様向けに「調整・交渉力」に関するご相談を無料でお受けしています。
お気軽にお問い合わせください。
↓
ご予約・お問い合わせ関連エントリー
-
 【調達部内会議】《Q&A》「営業の所要提示が遅くて交渉できない」と嘆く調達部員に、調達マネジャーはどう答えるべきか?
「部内会議で価格交渉の進捗を確認しても、『営業部門からの所要提示が直前すぎて、仕入先と交渉する時間が全くあり
【調達部内会議】《Q&A》「営業の所要提示が遅くて交渉できない」と嘆く調達部員に、調達マネジャーはどう答えるべきか?
「部内会議で価格交渉の進捗を確認しても、『営業部門からの所要提示が直前すぎて、仕入先と交渉する時間が全くあり
-
 【調達人材育成】ISOのための「力量管理表」で終わらせない!調達部員の強みを引き出し、組織力を高める「スキルマップ」活用のコツ
「ISO審査の時期が近づくたびに、慌てて力量管理表を埋めているが、事務局へ提出するための『書類づくり』が目的
【調達人材育成】ISOのための「力量管理表」で終わらせない!調達部員の強みを引き出し、組織力を高める「スキルマップ」活用のコツ
「ISO審査の時期が近づくたびに、慌てて力量管理表を埋めているが、事務局へ提出するための『書類づくり』が目的
-
 【調達組織風土改革】調達チームが自走し始める!調達組織風土を変えるために調達マネジャーが最初に変えるべき調達部員への「問いかけの仕方」
「関連部署からの急な依頼やトラブル対応に振り回され、調達マネジャーである自分自身が一番忙しく、本来取り組むべ
【調達組織風土改革】調達チームが自走し始める!調達組織風土を変えるために調達マネジャーが最初に変えるべき調達部員への「問いかけの仕方」
「関連部署からの急な依頼やトラブル対応に振り回され、調達マネジャーである自分自身が一番忙しく、本来取り組むべ
-
 【調達人材育成】調達部員の「考える力」を奪っていませんか?「答え」を教えすぎる調達マネジメントからの脱却
「良かれと思ってアドバイスをしているが、いつまでも調達部員が自分で判断せず、些細なことでも確認に来る・・・。
【調達人材育成】調達部員の「考える力」を奪っていませんか?「答え」を教えすぎる調達マネジメントからの脱却
「良かれと思ってアドバイスをしているが、いつまでも調達部員が自分で判断せず、些細なことでも確認に来る・・・。
-
 【調達マネジャーの心得】中日ドラゴンズ落合博満元監督に学ぶ!「俺のやり方」を押し付けない、個性を活かす調達部員の育て方
「調達部員を早く一人前にしようと熱心に指導しているつもりだが、なぜか自分の意図が伝わらず、期待したような成長
【調達マネジャーの心得】中日ドラゴンズ落合博満元監督に学ぶ!「俺のやり方」を押し付けない、個性を活かす調達部員の育て方
「調達部員を早く一人前にしようと熱心に指導しているつもりだが、なぜか自分の意図が伝わらず、期待したような成長
応援のチカラ
まずはお気軽にお問い合わせくださいね。
電話番号:090-4593-3959
受付時間:10:00〜18:00
定休日 : 土日祝
所在地 : 神奈川県川崎市中原区下小田中1-32-5 会社概要はこちら