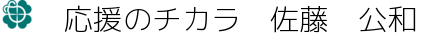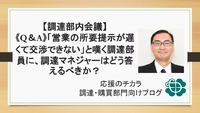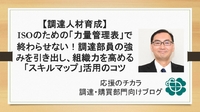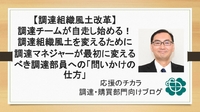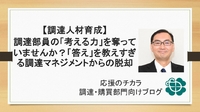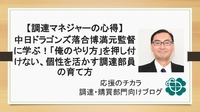- ホーム
- ブログ
- 「調達・購買部門」関連記事
- 調達・購買部員の教育方法と選び方のポイント
調達・購買部員の教育方法と選び方のポイント

- 調達・購買部員の教育を計画しているが・・・。
- いろいろな教育方法があるのでどう決めたらいいかわからない・・・。
- 調達・購買部員の教育方法とその選び方を教えてほしい!
調達・購買部員の教育を検討されている調達・購買部門長・マネジャーの方へ。「どんな教育」を「どんな方法」で行えばいいか悩みますよね。
まず、教育方法の選択肢を理解した上で、選び方のポイントを押さえておくことが大切ですよとお伝えしています。
今回は、調達・購買部員の教育方法と選び方のポイントについてお伝えしますので、ぜひご覧ください。
調達・購買部員の教育方法と選び方のポイント
教育の選択肢は主に3つ
まず、教育の選択肢を確認していきましょう。以下の3つです。
- OJT(On the Job Training)
- OFF-JT(Off The Job Training)
- SD(Self Development)
①OJT(On the Job Training)
職場での実務を通じて知識やスキルを習得させる人材育成手法で、調達マネジャーや教育係の先輩部員が新任部員や後輩部員をマンツーマンで指導する形式です。
②OFF-JT(Off The Job Training)
職場外で行われる研修や学習で、日常の業務から離れて行われる座学の集合研修や、eラーニングなどがあります。③SDとの違いは、会社側が用意した研修や学習であることです。
③SD(Self Development)
自己啓発という形で、調達・購買部員自らの意思で能力やスキルを向上させることを指し、社内外のセミナーへの参加、本や動画による自主学習、業務に関連する資格取得、 eラーニングなどがあります。また、セミナー参加費用の補助や資格取得時の報奨金支給を行い、自己啓発を促す制度を活用している企業もあります。
選び方のポイントは、「目的」を意識すること
選び方のポイントは、「目的」を意識することです。例えば以下のとおりです。
「目的」にあった選び方(例:取引先交渉に関する教育)
- 取引先交渉の実務について教育したい
OJT形式で、調達マネジャーや教育係の先輩部員が業務の流れに沿って指導する
- 取引先交渉に関する知識やスキルを体系的に教育したい
OFF-JT形式で、外部講師による研修やセミナーを受講する
- 調達部員の希望により取引先交渉スキルのレベルアップを図りたい
SD形式で、調達マネジャーと相談の上、本人が希望する研修やセミナーを受講する
その他の教育方法
その他にも教育方法はあります。例えば以下のとおりです。
部内勉強会開催
テーマを決めて、調達・購買部内で勉強会を開催するという教育方法です。例えば、取引先の倒産リスクに対応するために取引先の財務分析ができるようになるために、部内で勉強会を開催するというものです。調達・購買部員が担当する取引先を例に挙げながら話し合うことができると、より理解を深めることができます。
課題図書を決めて報告書を提出
課題図書を決めて報告書を提出するという教育方法です。調達マネジャーが学習してほしいテーマに関する課題図書を選び、期限を決めて調達・購買部員に報告書を提出してもらうという流れです。最近は、年に1冊も本を読まないという若い方も増えていますので、読書を習慣づけることにより、SD(自己啓発)を促していくという目的にされるのも効果的です。
まとめ
- 教育の選択肢は主に3つ(OJT、OFF-JT、SD)
- 選び方のポイントは、「目的」を意識すること
- その他の教育方法には、「部内勉強会」「課題図書を決めて報告書を提出」などがある
教育を選択する際は、「目的」を確認していただき、実務はOJT中心で難しい場合にOFF-JTも活用。体系的な知識やスキルを習得したい場合はOFF-JT中心に。調達・購買部員が主体的に学ぶ機会を持てるようにSD(自己啓発)を入れていくという形で3つの選択肢のバランスを意識しながら検討していただければと思います。
調達・購買部門の部門長様・調達マネジャー様向けに「調達・購買部門の人材育成」に関するご相談を無料でお受けしています。
お気軽にお問い合わせください。
↓
お問い合わせフォーム関連エントリー
-
 【調達部内会議】《Q&A》「営業の所要提示が遅くて交渉できない」と嘆く調達部員に、調達マネジャーはどう答えるべきか?
「部内会議で価格交渉の進捗を確認しても、『営業部門からの所要提示が直前すぎて、仕入先と交渉する時間が全くあり
【調達部内会議】《Q&A》「営業の所要提示が遅くて交渉できない」と嘆く調達部員に、調達マネジャーはどう答えるべきか?
「部内会議で価格交渉の進捗を確認しても、『営業部門からの所要提示が直前すぎて、仕入先と交渉する時間が全くあり
-
 【調達人材育成】ISOのための「力量管理表」で終わらせない!調達部員の強みを引き出し、組織力を高める「スキルマップ」活用のコツ
「ISO審査の時期が近づくたびに、慌てて力量管理表を埋めているが、事務局へ提出するための『書類づくり』が目的
【調達人材育成】ISOのための「力量管理表」で終わらせない!調達部員の強みを引き出し、組織力を高める「スキルマップ」活用のコツ
「ISO審査の時期が近づくたびに、慌てて力量管理表を埋めているが、事務局へ提出するための『書類づくり』が目的
-
 【調達組織風土改革】調達チームが自走し始める!調達組織風土を変えるために調達マネジャーが最初に変えるべき調達部員への「問いかけの仕方」
「関連部署からの急な依頼やトラブル対応に振り回され、調達マネジャーである自分自身が一番忙しく、本来取り組むべ
【調達組織風土改革】調達チームが自走し始める!調達組織風土を変えるために調達マネジャーが最初に変えるべき調達部員への「問いかけの仕方」
「関連部署からの急な依頼やトラブル対応に振り回され、調達マネジャーである自分自身が一番忙しく、本来取り組むべ
-
 【調達人材育成】調達部員の「考える力」を奪っていませんか?「答え」を教えすぎる調達マネジメントからの脱却
「良かれと思ってアドバイスをしているが、いつまでも調達部員が自分で判断せず、些細なことでも確認に来る・・・。
【調達人材育成】調達部員の「考える力」を奪っていませんか?「答え」を教えすぎる調達マネジメントからの脱却
「良かれと思ってアドバイスをしているが、いつまでも調達部員が自分で判断せず、些細なことでも確認に来る・・・。
-
 【調達マネジャーの心得】中日ドラゴンズ落合博満元監督に学ぶ!「俺のやり方」を押し付けない、個性を活かす調達部員の育て方
「調達部員を早く一人前にしようと熱心に指導しているつもりだが、なぜか自分の意図が伝わらず、期待したような成長
【調達マネジャーの心得】中日ドラゴンズ落合博満元監督に学ぶ!「俺のやり方」を押し付けない、個性を活かす調達部員の育て方
「調達部員を早く一人前にしようと熱心に指導しているつもりだが、なぜか自分の意図が伝わらず、期待したような成長
応援のチカラ
まずはお気軽にお問い合わせくださいね。
電話番号:090-4593-3959
受付時間:10:00〜18:00
定休日 : 土日祝
所在地 : 神奈川県川崎市中原区下小田中1-32-5 会社概要はこちら