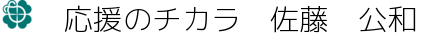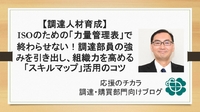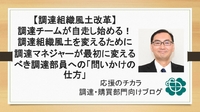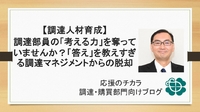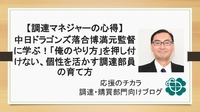- ホーム
- ブログ
- 「調達・購買部門」関連記事
- 【調達・購買】「下請法」親事業者の11の禁止事項とは?
【調達・購買】「下請法」親事業者の11の禁止事項とは?

- 新任の調達担当者が配属される予定があって・・・。
- まず、下請法について教えたいが・・・。
- どのように説明すればいいか教えてほしい!
このような悩みをお持ちの調達・購買マネジャーの方へ。
新任の調達担当者には下請法についてしっかり伝えておきたいですよね。
新任の調達担当者の対応次第では、後々トラブルやクレームに発展してしまうこともありますので注意が必要です。
親事業者の11の禁止事項とは?
まず、親事業者の11の禁止事項について見ていきましょう。
下請事業者が親事業者からの不当な取扱いを受けないようにするために、下請法では、親事業者に11の行為を禁止しています。
親事業者が下請法に違反した場合には、公正取引委員会が勧告や指導により、親事業者の違反行為をやめさせたり、下請代金の減額分を下請事業者に対して返還させたりしています。また、勧告が行われた場合、企業名などが公表されます。
11の禁止事項
(1)受領拒否の禁止
下請事業者に責任がないのに、発注した物品等の受領を拒否することです。発注の取消し、納期の延期などを理由に納品物を受け取らない場合も受領拒否に当たります。
(2)下請代金の支払遅延の禁止
発注した物品等の受領日から60日以内で定められている支払期日までに下請代金を支払わないことです。納品物品の検査等で日数がかかる場合でも、受領後60日以内に支払わない場合は支払遅延となります
(3)下請代金の減額の禁止
下請事業者に責任がないのに、発注時に決定した下請代金を発注後に減額することです。名目や方法、金額に関わらず、あらゆる減額行為が禁止されています。
(4)返品の禁止
下請事業者に責任がないのに、発注した物品等を受領後に返品することです。
(5)買いたたきの禁止
発注する物品・役務等に通常支払われる対価に比べて、著しく低い下請代金を不当に定めることです。現下のような労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの急激な上昇という経済環境においては、受注者からの要請の有無にかかわらず、発注者から積極的に価格転嫁に向けた協議の場を設けていくことが重要です。
(6)購入・利用強制の禁止
下請事業者に発注する物品の品質を維持するためなどの正当な理由がないのに、親事業者が指定する物(製品、原材料等)、役務(保険、リース等)を強制的に購入・利用させることです。
(7)報復措置の禁止
親事業者の違反行為を公正取引委員会や中小企業庁に知らせたことを理由に、その下請事業者に対して取引数量の削減・取引停止など、不利益な取り扱いをすることです。
(8)有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
親事業者が有償支給する原材料等によって下請事業者が物品の製造等を行っている場合、その原材料等を使って製造された物品の下請代金の支払日より早く、原材料等の対価を支払わせることです。
(9)割引困難な手形の交付の禁止
下請代金を手形で支払う際、銀行や信用金庫など一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付することです。
(10)不当な経済上の利益の提供要請の禁止
親事業者が自己のために、下請事業者に金銭や役務、その他経済上の利益を不当に提供させることです。下請代金の支払とは独立して行われる、協賛金や従業員の派遣の要請などが該当します。
(11)不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
発注の取消しや発注内容の変更を行ったり、受領した後にやり直しや追加作業を行わせたりする場合に、下請事業者が作業に当たって負担する費用を親事業者が負担しないことです。
まとめ
- 親事業者の11の禁止事項とは、下請事業者が親事業者からの不当な取扱いを受けないようにするために、11の行為を禁止している
- 11の禁止事項は、(1)受領拒否の禁止(2)下請代金の支払遅延の禁止(3)下請代金の減額の禁止(4)返品の禁止(5)買いたたきの禁止(6)購入・利用強制の禁止(7)報復措置の禁止(8)有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止(9)割引困難な手形の交付の禁止(10)不当な経済上の利益の提供要請の禁止(11)不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
新任の調達担当者が、下請法を理解しないせずに安易に取引先に対して「買いたたき」や「受け取り拒否」の交渉を行うことがないよう、しっかり伝えておきましょう!
研修担当者様、調達マネジャー様向けに「調整・交渉力」に関するご相談を無料でお受けしています。
お気軽にお問い合わせください。
↓
-
 【調達人材育成】ISOのための「力量管理表」で終わらせない!調達部員の強みを引き出し、組織力を高める「スキルマップ」活用のコツ
「ISO審査の時期が近づくたびに、慌てて力量管理表を埋めているが、事務局へ提出するための『書類づくり』が目的
【調達人材育成】ISOのための「力量管理表」で終わらせない!調達部員の強みを引き出し、組織力を高める「スキルマップ」活用のコツ
「ISO審査の時期が近づくたびに、慌てて力量管理表を埋めているが、事務局へ提出するための『書類づくり』が目的
-
 【調達組織風土改革】調達チームが自走し始める!調達組織風土を変えるために調達マネジャーが最初に変えるべき調達部員への「問いかけの仕方」
「関連部署からの急な依頼やトラブル対応に振り回され、調達マネジャーである自分自身が一番忙しく、本来取り組むべ
【調達組織風土改革】調達チームが自走し始める!調達組織風土を変えるために調達マネジャーが最初に変えるべき調達部員への「問いかけの仕方」
「関連部署からの急な依頼やトラブル対応に振り回され、調達マネジャーである自分自身が一番忙しく、本来取り組むべ
-
 【調達人材育成】調達部員の「考える力」を奪っていませんか?「答え」を教えすぎる調達マネジメントからの脱却
「良かれと思ってアドバイスをしているが、いつまでも調達部員が自分で判断せず、些細なことでも確認に来る・・・。
【調達人材育成】調達部員の「考える力」を奪っていませんか?「答え」を教えすぎる調達マネジメントからの脱却
「良かれと思ってアドバイスをしているが、いつまでも調達部員が自分で判断せず、些細なことでも確認に来る・・・。
-
 【調達マネジャーの心得】中日ドラゴンズ落合博満元監督に学ぶ!「俺のやり方」を押し付けない、個性を活かす調達部員の育て方
「調達部員を早く一人前にしようと熱心に指導しているつもりだが、なぜか自分の意図が伝わらず、期待したような成長
【調達マネジャーの心得】中日ドラゴンズ落合博満元監督に学ぶ!「俺のやり方」を押し付けない、個性を活かす調達部員の育て方
「調達部員を早く一人前にしようと熱心に指導しているつもりだが、なぜか自分の意図が伝わらず、期待したような成長
-
 【名古屋】2026年2月13日(金)「製造業における若手社員のための「報連相」と「聴き方・メモの取り方」習得セミナー」登壇のお知らせ
「上司からの指示をメモに取っているつもりだが、後で見返すと不明点が出てきたり、聞き逃しによる作業のやり直しが発
【名古屋】2026年2月13日(金)「製造業における若手社員のための「報連相」と「聴き方・メモの取り方」習得セミナー」登壇のお知らせ
「上司からの指示をメモに取っているつもりだが、後で見返すと不明点が出てきたり、聞き逃しによる作業のやり直しが発
応援のチカラ
まずはお気軽にお問い合わせくださいね。
電話番号:090-4593-3959
受付時間:10:00〜18:00
定休日 : 土日祝
所在地 : 神奈川県川崎市中原区下小田中1-32-5 会社概要はこちら